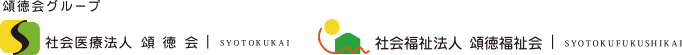ADL向上への働きかけ
食事は身体の栄養状態の改善・体力つくりの側面だけでなく、日常生活の中の楽しみの一つにあたります。頌徳会グループでは患者さん・ご利用者が食事を食べる喜びを得ていただくために必要な生活リハビリテーションを提供しています。
食事を美味しく楽しんでいただくために
頌徳会グループでは多職種が連携し、患者さん・ご利用者の食事形態のレベルアップに向けて取り組んでいます。食事形態のレベルアップにより、『栄養状態の改善』『QOL(生活の質)の向上』『ご自宅での介助者の介護負担軽減』『リハビリテーションに必要な体力の維持』が期待できます。
『食事』に関する生活
リハビリテーションの取り組み
日野病院での取り組み
退院後を見据えた場合、「一口大」「粗刻み」「ムース」などの特別な食事形態の準備は、‘独居で障害を抱えたまま1人で調理することが難しい’‘高齢介護者と2人暮らしで、介護者は細かな作業が難しい’などの理由で、食事の準備が困難なケースもあります。そのような背景から、全入院患者さんを対象に多職種協働による最適な食事形態への見直しを定期的に実施しています。
Point
医師・看護師・言語聴覚士・栄養士が連携し、患者さんの食事形態のレベルアップへの共通意識を持って、様々な視点から介入することで、より高い食事形態へのレベルアップを図るように改善しています。
鮭の醤油こうじ焼き
-

ムース食

-

粗刻み

-

一口大
-

普通食
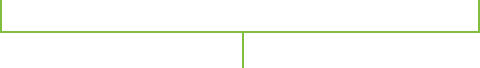
![]() 日野病院では、お食事を美味しく楽しんでいただく観点から、介護食「あいーと」を導入しています。
日野病院では、お食事を美味しく楽しんでいただく観点から、介護食「あいーと」を導入しています。
頌徳会グループ各施設での取り組み
ご利用者の経口移行・経口維持に向けて、食事時の姿勢、日々の健康的状態、その日の心身状況、食事動作について、どこに問題があるのかを多職種協働で評価しています。また食事には ‘味’‘見た目’‘香り’等の様々な感覚に着目することも、食事摂取時のキーポイントになります。ご利用者の『食べる楽しみ』に配慮し、安全性を重視した多職種協働による取り組みを行っています。
普通食の調理提供方法への工夫
病院・施設等で一般的な大量調理方式を採用すると、調理後から提供までに時間が掛かる等により、食事が冷めたり、固くなる等の課題がありましたが、調理提供方法を見直すことでレストランのように温かく柔らかいまま提供できるよう工夫しています。
食事形態レベルアップのメリット
- 食事に対して積極的になり、栄養状態の改善につながります。
- 調理するご本人やご家族・介助するご家族の介護負担の軽減につながります。
- 食事への満足感が向上することで、QOL(生活の質)が向上します。
- 日常生活に必要な体力作りの促進が期待できます。
頌徳会グループの食事へのこだわり
頌徳会グループが考える『美味しい食事』『安全な食事』とは、食べ物を目にした時に、それを食べ物と判断できて食欲がかき立てられて食べたいと感じることが、『食事の第一歩』と考えています。
-
1.先行期

食材を目にして食べられるかどうか判断する
-
2.準備期

食べ物を唾液と混ぜ合わせて呑み込みやすい形にまとめる
-
3.口腔期
実際に飲みこんでいく
-
4.咽頭期
咽頭から食道に食材を選ぶ
-
5.食道期
食材を食道から胃へ送っていく

![]() 1.先行期(認知期)で、視覚・嗅覚から「美味しそう」「食べたい」と感じ、食べるための心の準備が進み、
1.先行期(認知期)で、視覚・嗅覚から「美味しそう」「食べたい」と感じ、食べるための心の準備が進み、
2.準備期(咀嚼期)で、「自然とあふれでるだ液」と混ぜ合わせて粘りを持たせ、飲み込みやすい形状にまとめ上げる
この飲み込むまでの準備段階にこだわりを持って、「食べたい!」と感じてもらい、実際に「美味しい食事を楽しく召し上がっていただく」ことが頌徳会グループの方針です。
頌徳会グループが食事でこだわっている
ポイント
- ‘味’‘香り’‘見た目’ができる限り普通の食事と変わらないものを提供する。
- 咀嚼・嚥下が困難な方にも安心して食べられる柔らかい食事を提供する。
一般的には咀嚼・嚥下困難な方へは、極キザミ食・ムース食等の介護食が採用されるケースが多いですが、頌徳会グループでは普通の食事同様に‘味’‘香り’‘見た目’が変わらない食事を召し上がっていただけるようイーエヌ大塚製薬(株)が開発した介護食「あいーと」を導入しています。
一般的な介護食
お事はとりやすくなるが、「食欲が出ない=低栄養状態を招く」「飲み込む能力が低い方には誤嚥リスクが上がる」可能性もあります。
サバの塩焼きと付け合わせ
-

極キザミ食
-

ムース食
介護食「あいーと」
普通の食事と変わらないしっかりとした味付けです。出汁の風味や香味・コクを追求し、香りや風味も楽しめます。
-

肉じゃが
イーエヌ大塚製薬㈱独自技術 酵素均質浸透法
見た目はそのままですが、スプーンで軽く押しつけただけでつぶせる柔らかさになっています。
-


れんこん
-


牛肉
-


鮭